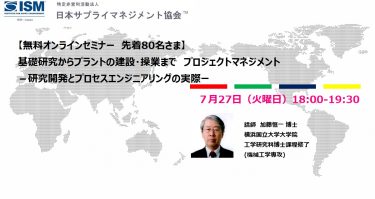5. 内閣府景気ウォッチャー調査
内閣府景気ウォッチャー調査
5月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差1.0ポイント低下の38.1となった。
家計動向関連DIは、飲食関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、製造業等が上昇したことから上昇した。雇用関連DIについては、上昇した。
5月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差5.9ポイント上昇の47.6となった。
家計動向関連DI、企業動向関連DI、雇用関連DIが上昇した。
なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差3.0ポイント低下の36.4となり、先行き判断DIは前月差5.3ポイント上昇の46.8となった。
今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しさが残る中で、持ち直しに弱さがみられる。先行きについては、感染症の動向を懸念しつつも、ワクチン接種の進展等による持ち直しへの期待がみられる。」とまとめられる。
※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。
2.物流・購買・調達・サプライチェーン関連記事抜粋:令和3年5月1日~5月31日
| 主題 | 概要 | |
| 1 | トヨタ、電池投資1600億円 | EV値下げへ自前生産 日産、中国系と日英に新工場 |
| 2 | ユニクロ、米輸入差し止めに見解 | シャツの綿 中国以外で生産:新疆綿は使わず |
| 3 | ニトリ、島忠ブランド廃止 | 海外成長戦略、焦点に 出店は倍増、5年後1000店へ |
| 4 | 新疆綿、使用中止の動き | ワールドやミズノ ウイグル問題で |
| 5 | 衣料・小売り、履歴確認厳格に | 供給網、人権問題リスク アダストリア工場情報公開 ワークマン素材も外部監査 |
| 6 | 台湾IT部品不足が深刻 | デジタル景気に影響も PC・スマホ生産停滞、長期化の恐れ |
| 7 | 武田の創薬、競合とも組む | 欧米勢対抗「連携」テコに iPS薬の実用化急ぐ:GAFAとも協力 |
| 8 | 日立、グローバル化加速 | 社長に小島氏 研究・構造改革で実績 |
| 9 | トヨタ快走、供給網強く | 生産回復 いち早く カンバン深化、半導体確保へ長期戦略も |
| 10 | 日本電産、EV生産20社連合 | 異業種の複数社と交渉 部品一括受託へ中国に集積拠点 |
≪用語解説:記事内の用語を確認します≫
| 新疆綿 |
| 新疆綿とは、新疆ウイグル自治区で栽培される綿(コットン)。コロナ禍前の世界の綿花生産量(2018〜2019年)トップ3は、1位が中国(604万トン)、2位がインド(535万トン)、3位が米国(400万トン)で、中国は全世界の生産量(2574万トン)の23%を占めている。また、新疆の綿花生産量(511万トン)は中国生産分の内84.6%に達しており、新疆綿は、世界の綿生産量の19.8%を占める巨大産業。新疆綿は繊維長が長い「超長繊維綿」で、滑らかさや光沢感があるのが特徴だ。色が白く、染色しても発色が良い。かつてはギザ綿(エジプト産)、スーピマ綿(米国産)と並ぶ世界三大綿と呼ばれていたが、エジプトでは観光やスエズ運河の通航料などに収入がシフトしており、綿花は殆ど栽培されなくなっているのが現状。新疆綿とスーピマ綿が二強の状態になっている。 しかも、価格は比較的安価だ。 鄧小平時代の1980年代、豊田通商が日本の農業技術、主に点滴灌漑という技術を導入。これをきっかけに、新疆では生産効率が高まり、現在では米国大規模農場の2倍の生産効率となった。それから40年、今日では欧米を中心に新疆綿の使用が問題視されるようになった。背景の一つには、中国政府が新疆ウイグル自治区でイスラム教徒が大部分を占める少数民族ウイグル族を収容施設に収容し、民族迫害をしていると2018年頃から欧米のメディアで報じられるようになったためだ。特にBBCのジョン・サドワース(John Sudworth)記者が書いた「China’s ‘tainted’ cotton(中国の汚れた綿)」が2020年12月に公開されたことが大きい。 |
| EV用電池投資 |
| 日産自動車は中国系企業と組み、日英に2つの新工場を建てる。トヨタ自動車も2022年3月期の電池への投資を1600億円と前期比2倍にし、欧米勢も相次ぎ電池大手との提携を決めた。電池はEV価格の5割程度を占める最重要部品だ。自社生産などで数量を確保しつつコストを低減し、EVの販売競争に備える。日産と仏ルノー、三菱自動車の日仏連合は、今回新設を決めた日英の2工場のほか、フランスやスペインなど欧州や米国、中国でも新たに4つの電池工場の建設を検討している。欧州では仏ルノーが韓国のLG化学と、中国では日産が中国の寧徳時代新能源科技(CATL)とそれぞれ組む案が有力だ。3社は車載電池の規格を共通化することでも合意した。規格を統一して大量生産しやすくし、生産コストを減らす。日産は30年をめどに日英中の完成車工場の一部でガソリン車の生産をやめ、EVとハイブリッド車(HV)の専用工場に転換することも検討している。他の自動車大手も一斉に生産能力の増強に動く。トヨタはパナソニックと共同出資する電池子会社が兵庫県や中国・大連の工場で生産ラインを増設する。独フォルクスワーゲン(VW)も新興企業と組んで30年までに欧州で6カ所の電池工場を建設する。米フォード・モーターは韓国のSKイノベーションと、米ゼネラル・モーターズ(GM)もLG化学とそれぞれ提携し、米国に合弁工場を設ける。各社が電池をかき集めるのは、EVの急激な伸びが見込まれる一方、電池の供給力が追いついていないためだ。 英調査会社のLMCオートモーティブによると、EVの世界販売台数は30年に2334万台に達し、20年の10倍になると予測する。一方で20年の車載電池の生産能力は約400万台分しかない。生産能力の増強を急がないと、EVの販売競争で取り残される。課題は電池の価格だ。世界的な「脱炭素」の流れでホンダが40年にガソリン車の全廃を打ち出し、GMや独ダイムラーなども車種をEVなどに絞る方針を決めた。現在のガソリン車では最重要部品のエンジンを効率的に作る能力が、各社の競争力の源泉となっている。他社に先駆けて価格を引き下げられるか。EVでの自動車メーカーの優勝劣敗を電池が握る。 |