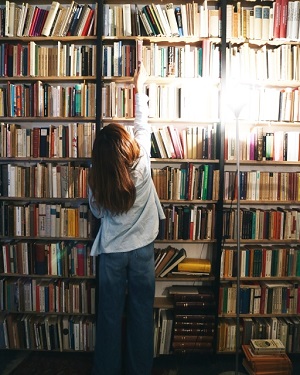⑤ 内閣府景気ウォッチャー調査
V 内閣府景気ウォッチャー調査
12月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差11.3ポイント低下の34.3となった。家計動向関連DIは、飲食関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、非製造業等が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、低下した。
12月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差0.6ポイント上昇の37.1となった。
雇用関連DIが低下したものの、家計動向関連DI及び企業動向関連DIが上昇した。
なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差9.6ポイント低下の36.5となり、先行き判断DIは前月差0.0ポイントの36.1となった。
今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、このところ弱さがみられる。先行きについては、感染症の動向に対する懸念が強まっている。」とまとめられる。
※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。
2.物流・購買・調達・サプライチェーン関連記事抜粋:12月1日~12月31日
| 主題 | 概要 | |
| 1 | コロナ下、半導体奪い合い | トヨタ:代替調達を検討 ゲーム機:生産に懸念も |
| 2 | コロナ下「勝ち組」に綻び ゴム手袋首位トップグローブ | 労働環境に厳しい目 収束なら設備重荷に |
| 3 | セブン&アイ、宅配網共有 | グループで百貨店から外食まで コンビニを拠点に |
| 4 | ベトナム対米黒字 日本越え | 中国から生産移管 米は「為替操作国」で警戒 |
| 5 | コロナでもカイゼン続く | 位置情報で工場の稼働分析;感染対策徹底ムダ省く トヨタ、第一波出社9割 |
| 6 | インド農業新法、反発拡大 | 取引自由化に不安、デモ続く モディ改革路線に試練 |
| 7 | コロナワクチン超低温輸送 米サーモキングが開発 | 米ファイザー製ワクチン 摂氏マイナス70度で輸送・保管する必要あり |
| 8 | 米ファイザー・独ビオンテック新型コロナウイルスワクチン | 米食品医薬品局(FDA)緊急使用許可の申請を受け1回の投与でも一定の予防効果が見られたと公表 |
≪参考≫
| サーモキングThermo King |
| 米国の冷凍・冷蔵機器メーカー。米インガソル・ランド社(Ingersoll Rand)の一部門で、ミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、車載・コンテナ用冷凍・冷蔵装置において全世界で高いシェアを誇る。日本法人の本社は東京都品川区。主力商品は貨物自動車や海上コンテナの冷凍・冷蔵装置、バス用の空調機器で、売上高12億ドルの内75%近くはトラックやコンテナ用の冷凍・冷蔵装置が占めている。2020年アイルランドの空調機大手企業トレーン・テクノロジーズと米インガソル・ランド(旧:Gardner Denver Inc.)が合併し、インガーソール・ランド インコーポレイテッド(Ingersoll Rand Inc.)となり、サーモキングはトレーン・テクノロジーズの子会社となっている。世界6カ国にに9つの製造工場を持ち、 800以上のサーモキングディーラーがパートナーとして全世界を網羅している。 |
| 為替操作国 Currency manipulator |
| 米国財務省が提出する為替政策報告書に基づき米国議会が為替相場を不当操作していると認定した対象国。財務省は、1988年から毎年2回議会に対して為替政策報告書を提出している。それに基づき、対米通商を有利にすることを目的に為替介入し、為替相場を不当に操作している国に対してと議会が為替操作国と認定する。為替操作国に認定された国は、米国との間で二国間協議が行われ通貨の切り上げを要求される。米国は必要に応じて関税による制裁を行う。また為替レートの影響が大きい財界から財務省に対して認定を要求することがある。1980年代から1990年代にかけては、台湾・韓国が為替操作国に認定されたことがあるが、中国を為替操作国に認定した1994年7月以降、為替操作国に認定された国は2000年代に入ってもなかった。2016年4月29日には、財務省は為替介入を牽制するために中国・台湾・韓国・日本・ドイツの5カ国を監視対象とする為替監視リストを発表し、同年10月にスイス、2018年4月にはインドを新たにリストに加えた。2019年5月にはアイルランド、イタリア、ベトナム、シンガポール、マレーシアを追加してスイスとインドを除外した。2019年8月6日、米国との貿易摩擦の中で中国は1994年7月以来初となる為替操作国に認定されたものの、2020年1月13日に第1段階の貿易合意に至ったことを受けて為替操作国の指定を解除した。同年12月16日にはベトナムとスイスを為替操作国に認定し、タイと台湾とインドを為替監視リストに追加した。 |
| インド農業新法:サプライチェーンの問題 |
| インド農業部門は数多くの課題を抱えている。農家の零細・小規模経営や技術導入の遅れが生産性向上を阻害すると伴に、サプライチェーンにおける非効率な市場とインフラ整備の遅れが農家の収益性を損なっており、気候変化や農業金融へのアクセスが難しいことが農業を不安定なものにしているため、農民は貧困状態から抜け出せず、高成長を続ける非農業部門との間で所得格差が広がっている。こうした課題は長年にわたり政府も取り組んできたが、未だ解決には至っていない。非効率なサプライチェーンの問題は民間企業や農業生産者団体/農業生産者企業の係わり、eNAMの導入などにより進展が見られるものの、総じて成果の出るまでに時間のかかる課題が多く、短期間で貧困に苦しむ農家の負担を和らげることは難しい。また、輸送インフラや貯蔵・加工施設の問題も大きい。多くの地域では安全な輸送インフラが整っていないために商品の形が損なわれるほか、配送が遅れがちになる。また農作物を収穫した後、農家や市場の保管状態が悪いためにネズミや雑菌の被害、浸水被害などを受けやすく、特に果物や野菜などの生鮮食品については約30~40%の農産物が廃棄されてしまっている。更に貯蔵施設の利用は大規模農家に止まっており大半の農家は現金化を急いでいることもあり農作物の供給が過多になる収穫期に低価格での販売を強いられ、利益が目減りしてしまっている。農業政策が進まない背景には、インドの政治制度がある。農業政策の権限は州政府にあるため中央政府の掲げる農業政策が実行段階で州の特殊事情に合わせて中身を変えられてしまう。連立政権内の意見対立12のために抜本的な対策を実行に移すことが難しいこともあるほか、農業部門に関連のある省庁が少なくとも12以上もあるために政策調整に時間がかかることも関係している。 |