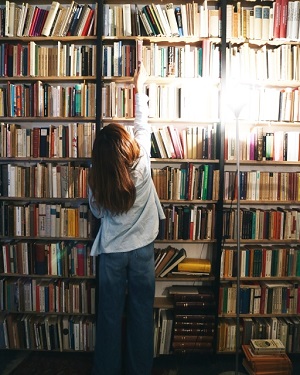3.おわりに
「医師と業界の癒着、後たたず」という記事を読み、筆者の過去の経験が蘇った。記事概要は次の通り:医療機器メーカーなど業界と医師の癒着は後を絶たない。2017年にも公立病院の臨床試験補助業務を巡り、当時部長だった医師が第三者供賄容疑で逮捕された。医療の高度化で検査や手術に用いる機器は高額になり、採用の可否はサプライヤーの収益に大きな影響を及ぼす。ある国立大病院の幹部の話では、大学病院の教授クラスには広い裁量権が認められている。競合他社としのぎを削りながら販売先の確保を目指すサプライヤー多数が近づき、不適切な関係に陥る事態も起こり得るとのこと。医療機器の調達をめぐって自身が代表を務める法人の口座にメーカー側から現金200万円を振り込ませたとして、大学病院臨床麻酔部の元教授ら医師2人が第三者供賄の疑いで逮捕された。贈賄容疑で医療機器メーカー社員3人も逮捕された。警察捜査本部によると、容疑者は医療機器メーカーの機器が納入されやすいような仕様書を大学に提出。2019年以降に同機器の一般競争入札に参加したのは、同社製を扱う業者1社だけだったと言う。同院は6年間で約1億7千万円をかけて同機器を入れ替える計画が背景にある。容疑者らは現金を職場の飲食費などに充てたとみられる。筆者から見れば問題は三点ある:
- 病院内に購買調達を専門に扱う部署がないこと
- 医師の作る仕様書を評価する人材がいないこと
- 設備投資計画のガバナンス(企業統治)が効いていないこと
1については地方自治体や政府霞が関官庁でも多く見られることで民主党政権時代に筆者も行政刷新会議に呼ばれ、件の民間調達について話をしたことがある。古くから特定の業者が官庁内に入り込んでおり、排除が難しいと感じた。2について民間企業でも研究者や博士号を持つ新人研究員の作る仕様書には特定のサプライヤーが裏にいると見まがうものも散見された。つまり、当該サプライヤーが受注できるような仕様書をサプライヤーに故意に作らせている訳だ。3では院内の設備投資計画を統率する部署がクロスファンクショナル体制で全院内を纏め切れていないことだろう。ここでも社内、院内の力関係が垣間見える。前者では博士号を持つ研究者、後者では医師であろう。日本のある製薬会社、化粧品会社では、元研究員・調剤員が購買部門に派遣され仕様チェックを行うと聞いたことがある。購買社員の教育もさることながら複数部門横断組織体制の運営の重要性を痛感している。
| 第三者供賄罪 |
| 公務員が職務に関して請託を受け、自分以外の第三者を受領者として金品などの賄賂を供与させた場合に成立する。公務員以外に渡された金品でも、公務員の職務行為と対価関係があることを明確にするため、請託が要件とされている。法定刑は5年以下の懲役。 |
月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA
特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会