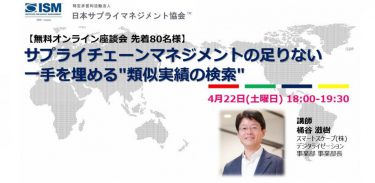3.おわりに:
昨年の弊法人年次大会で米国弁護士を招聘し講演してもらったが、先週再度WEB研修会があったので受講した。日本企業を震撼させるFCPA実例が具体的に紹介され、当該企業の経営陣はどう思ったのか気になるところだ。受講した内容をざっとおさらいする:
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act):企業が外国の公務員や政治家に賄賂を支払って事業を得ることを禁じる米連邦法
The FCPA は、以下の者に適用される
- 米国で株を発行し、同国内で何らかの関係があるもの。たとえ事業は米国外で行っているとしても;
- 米国に関連のある外国企業と米国内の経営陣
- 仲介に入る第三者
二つの管轄当局がFCPAを執行している
- 米国の司法省の詐欺に関する部局 (DOJ):米国で上場している企業、その役員、取締役、従業員及び、同企業のためのエージェントに対する刑事的な執行を担当する部局
- 証券取引委員会の法執行部 (SEC):米国で上場している企業、その役員、取締役、従業員及び、同企業のためのエージェントに対する民事的な執行を担当する局
FCPA の刑罰
個人
- 最長5年の拘禁刑
- 10万ドルを最高額とする刑事罰としての罰金
- 1万ドルを最高額とする民事罰としての罰金
- 故意の違反であれば、最長20年の拘禁刑と500万ドルの罰金
企業
- 200万ドルを最高額とする刑事罰としての罰金
- 1万ドルを最高額とする民事罰としての罰金
- 利益の吸い上げ
- 故意の違反であれば、最高2500万ドルの罰
日本企業の違反事例
1)パナソニック株式会社(2018):他の申し立てとともに、同社は、Middle East 航空との契約交渉の際に、外国公務員にコンサルタントになってくれるよう申し出た。そのほか、中国で13のサブエージェントに700万ドルを越える支払いを与えた。
罰金:2億8000万ドル(約370億円)
同社は、DOJやSECから協力に対しての利益を得られなかった。というのも、会社は申告の数年も前に FCPA違反について気づいていたからである。
2)日揮株式会社(2011):同社は、ナイジェリアでの液化天然ガスの入札と契約の実行の合弁会社のパートナーとの連携でDOJ曰く、同社は当初協力しなかったが、最終的には協力したと述べた。
罰金:2億1880万ドル(約285億円)とDPAの締結
「Deferred Prosecution Agreement (DPA)」は、検察官と被疑者との間で締結される合意であり、被疑者が特定の条件を遵守すれば、検察官は犯罪訴追を見送るという制度。「起訴猶予合意」「訴追延期合意」などと訳される。
3)丸紅株式会社 (2014):同社は、Alstom社とインドネシアで電力事業への入札のためにパートナーとなった。金額の一部が契約の成功に影響を及ぼすために用いられる可能性が高いことを知りながら、コンサルタントに支払いを行った。
和解:8800万ドル(約119億円)和解金と、経営陣の起訴
DOJはMarubeniに対し、協力を拒んだこと、効果的なコンプライアンスプログラムを有していないことに加え、過去の刑事罰を伴う不適正な行為について非難した。同社経営陣は起訴陪審で起訴が決定したがその後の情報はない。米国の法領域に入っていない可能性がある
4)株式会社ブリヂストン(2011&2014):同社は、マリンホースの市場における価格協定と市場分割を通してのFCPA違反と米国の反トラスト・シャーマン法違反で有罪の答弁を行った。DOJの詐欺部局と反トラスト法部局は、共同で作業を行い、同社が協力的であったことを引用して、合計2800万ドル(約38億円)での和解に達した。
2014年、自動車部品に関する価格協定に対し、反トラスト法違反で7番目に高額となる4億2500万ドル(約574億円)を同社に課した。というのも2011年の両法の捜査時にこの不正行為を開示しなかったことによる。反トラスト部局は、何度も繰り返す犯罪者が、反競争的なその他の行為について、開示をしない場合には、強硬路線をとると述べた。
5)日本ガイシ(日本碍子)株式会社(2015):米司法省は、同社が自動車部品の価格操作による反トラスト法違反の疑いを認めたと発表した。同社は6530万ドル(約78億円)の罰金を支払う。司法省は、日本ガイシが証拠隠滅などにより当局の捜査を妨害した疑いもあり、この件でも同社が有罪を認めるだろうとしている。司法省の発表によると、同社は競合他社と共謀した不正な入札によって、顧客である自動車メーカーへの納入価格を固定した疑いを認めた。確認できるだけで2000年7月から2010年2月まで不正を働いていたという。証拠隠滅による捜査妨害に関しては、幹部と社員が電子ファイルを削除したり、幹部のコンピューターを取り換えたりした疑いがあるという。紙の資料を破棄し、当局の捜査に対して情報を伏せたともしている。価格操作を認めたのは、自動車の排ガス浄化に使うセラミック触媒で、米ゼネラル・モーターズ、トヨタ自動車、日産自動車などに納入した。
以上のように大きな五つの例を挙げていたが、今後、日本企業はどのように対処すれば良いのか。これらの事例から学ぶべきことは次の通りと言う:
①もしある(法)領域で不適正行為があれば、他の違反もあることが検討される必要がある。DOJ は(株)ブリヂストンに対し、不適正行為の後に数年後に焦点が当てられた、他の不適正が申告されなかったことを責めた。一般に、企業は、捜査がなされている間でも、関係する全ての地域において、同時に自主申告すべきである。その企業が事務所を置いていたり、同地で事業を行っている全地域での自主申告。全ての国で、矛盾なく、捜査機関にアプローチできていることを確実にするために、弁護士間の協力が必要である。
②司法省は、日本の微妙なビジネスや社会、文化への理解や共感を有していないと考えられる。FCPAでは、贈答やその他の社会的な相互の関係については、慎重に精査されるもので日本ではかような贈答は長く確立した伝統であるというのは防御とならない。また、NOと言わないというのは同意していたものと解釈され得るから要注意だ。
③法令遵守のための研修プログラムは、重要である:特に特化した法務部を持たない小規模や中規模の企業には大変重要である。営業部門のスタッフやその上司は、上位の経営陣とは違う研修が必要。というのも彼らの挑戦している関心事は異なっているからである。不正行為があった場合、法令遵守の研修をすることにより、米国政府は、罰の軽減を検討してくれることもある。
皆さんの参考になったであろうか。マスコミであまり取り上げられない事案であるが、当の本人は個人に対する量刑であり「会社のためにやった」は全く通じないことを肝に銘ずるべきである。
以下余白
月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA 特定非営利活動法人