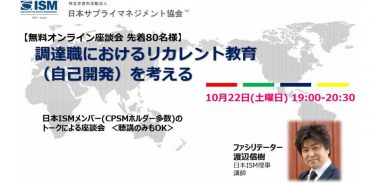3.おわりに:
中抜きという言葉が蔓延ってきた。先月も本稿で記述したが、東京五輪組織委員会のガバナンスが腐敗していたという事実からこの用語が改めて世に出てきた。中抜きの定義は、ビジネス領域では取引の間に不必要に仲介者が入って手数料などを取ること、もしくは仲介者を省略して直接取引することの両方の意味がある。元来は、中を抜き取ること、中を抜き取ったものだった。仲介者、中間業者が関わり、支払う手数料やマージンの総額が過度に高額になることを非難して「中抜き業者」と呼ばれている。手数料の総額として高額であることを第三者が「中間業者による不当な利益搾取」として非難する際に用いられるが、個々の取引間の手数料としては適正であることも多い。
もう一つは、流通や物流において卸売業者を介さずに生産者と販売者もしくは消費者が直接取引する際に用いられ、メーカーが消費者に商品を直販するなど、無形サービスのため物流が不要になったものなどで見られる現象である。欧米では、日本の商習慣において日本の流通コストは諸外国よりも高いとされる。その理由は販売会社の数が多過ぎ、多くのムダが発生しているからである。中抜き排除など産業構造を単純にするだけで賃金は大幅に上昇し、余剰となった労働力が他の生産に従事すれば、GDPの絶対値も増える。一方で彼等を活用する価値は十分にあると考えている。仲介者や卸売業者、代理店などの存在そのものや手数料の仕組みを否定するべきではないと思う。いわゆる役割分担という概念で、役割を果たさない中間業者こそ排除されるべきであると考えたい。
今般、政府の持続化給付金事業を受託した組織が、業務を外部企業に再委託していたことが問題視されている。税金を使った事業であることから世間の批判を集めることになったが、業務を請け負った企業が一定の利益を控除したのち、別の組織に再発注するという、いわゆる「中抜き」や「丸投げ」は、日本の企業社会において特段、珍しい光景ではない。残念ながら、この商習慣は重層的な下請け構造と密接に関係しており、日本の生産性を引き下げる要因の一つとなっている。
例えば、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が元請けとなった持続化給付金事業で、関与した企業は9次下請けまでで500社を越えたと言う。不透明な多重下請けは今回の問題の焦点の一つだった。持続化給付金のように前例のない巨大事業を受注できる企業は限られ、今回は同種事業の受注実績のあるサ協が、経産省側に重宝がられた面がある。だが、発注する政府自治体にとっては外注が増えればそれだけ予算の無駄につながる懸念もある。
このような外注や中抜きは、民間企業でも行われるが、政府自治体の者とは違い、私企業では血税が問題にならない。しかしながら、民間企業と言えども、外部の利害関係者が黙っている訳はない。企業経営の透明性が問われている現在、経営者は、監査役や第三者の目をしっかり意識しなければならない。
以下余白
月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA 特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会