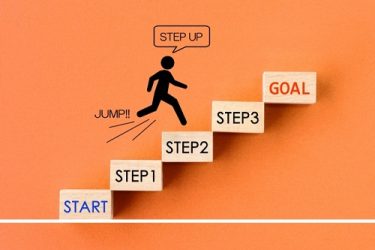5. 内閣府景気ウォッチャー調査
V 内閣府景気ウォッチャー調査
8月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差13.7ポイント低下の34.7となった。
家計動向関連DIは、飲食関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、非製造業等が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、低下した。8月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差4.7ポイント低下の43.7となった。家計動向関連DI、企業動向関連DI、雇用関連DIが低下した。なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差13.4ポイント低下の34.3となり、先行き判断DIは前月差5.4ポイント低下の41.7となった。
今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、持ち直しに弱さがみられる。先行きについては、内外の感染症の動向に対する懸念が強まっているが、ワクチン接種の進展等による持ち直しの期待がみられる。」とまとめられる。
※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。
2.物流・購買・調達・サプライチェーン関連記事抜粋:令和3年8月1日~8月31日
| 主題 | 概要 | |
| 1 | バイオ薬品、資材が不足 | ワクチン向け需要急増受け 独メルクなど培養バッグの増産急ぐ |
| 2 | 東南アジア、車部品の減産拡大 | 半導体や車載電線、感染増で トヨタなど調達厳しく |
| 3 | 半導体投資、12兆円に拡大 | 世界10社、今年度3割増 安定調達へ政府支援も |
| 4 | 東南アジア感染、日本の食に影 | 生産や物流停滞、卸値上昇 マーガリン値上げ、タイ産鶏肉、高値圏 |
| 5 | ファーウェイ製中国部品が倍増 | スマホ分解:制裁で国内調達6割 中核半導体:米国産在庫頼み |
| 6 | 東南アジア、外国人就労厳しく | 自国民の雇用確保へ条件見直し 日本企業、駐在員派遣に壁 |
| 7 | 三菱ケミカル、米で1000億円投資 | 日本企業「バイ・アメリカン」念頭 対米投資、1-3月4割増 |
| 8 | IT・部品、進む中国依存 | 15品目でシェア3割増 供給網見直し難しく |
| 9 | 東南アジア供給網、デルタ型で寸断 | 各国で規制、トヨタは工場停止 車・電機 日本にも影響 |
| 10 | 中国政府調達、国産を優先(バイチャイナ) | 医療機器など315品目広範に 対中輸出、影響大きく |
| 11 | バッテリーメタル、価格急騰リスク | リチウムやコバルト、EV向け需要増 代替品の普及がカギに |
| 12 | 調達網の人絹侵害 排除 | 花王や塩野義、取引先調査 世界基準 官民で対応 |
| 13 | 外国人材に日本がフラれる日 | 途上国GDP7000ドルが転機 中国と争奪も |
| 14 | 3Dプリンターで住宅建築 | 米新興、僅か10日で完成 臓器や代替肉、用途拡大 |
≪用語解説:記事内の用語を確認しましょう≫
| バッテリーメタル |
| リチウムやコバルト、ニッケルなど電気自動車(EV)の車載電池に必要な「バッテリーメタル」の価格がさらに上昇するリスクが警戒されている。足元のEVの販売増に加え、今後の本格普及で需要が急増し、価格がもう一段跳ね上がる可能性があるためだ。価格急騰を懸念する需要家サイドは自ら資源確保や希少な金属の使用を減らした代替品の開発を急いでいる。国際エネルギー機関(IEA)は「地球の気温上昇を2度より低く抑える」シナリオに基づくと、2040年にリチウムの総需要は20年比で42倍、コバルトで同21倍、ニッケルで19倍に増加すると試算する。価格高騰を懸念する自動車や電池メーカーは自ら資源の確保に動き出している。現状ではナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池よりもエネルギー密度が低くEVに向かないとの見方が多いが、今後の性能向上次第で将来のリチウムの需要を抑制できる。コバルトとニッケルを使わずに安価に作れるリン酸鉄リチウム(LFP)電池は既に実用化され、独フォルクスワーゲンが価格を抑えたエントリーモデルに採用する。EU(欧州連合)で進むリサイクルの動きも需給逼迫を緩和しうる。将来的に循環型のバッテリー産業が実現すれば、域内の再利用が増え、天然資源への依存度を下げられる。実際に代替電池やリサイクルが普及すれば、価格高騰の抑制も期待できそうだ。 |
| 培養バッグ |
| 再生医療のバリューチェーンは、再生医療製品サービスを開発、提供する企業を中心に、さまざまな技術を保有する周辺産業によって支えられており、日本が誇るものづくりの技術の活用が期待されている。再生医療の治療においては、採取した自家、他家細胞を培養する必要があるが、そのためには、細胞培養のための培地、試薬、培養容器などの消耗品類、無菌性を担保しながら遺伝子導入を行う細胞加工施設(CPC:セルフプロセッシングセンター)、加工した細胞を培養する細胞培養機器や加工した細胞の品質検査を行う細胞評価機器、また、細胞の採取から移植までのすべてのプロセスにかかわる細胞や組織の輸送サービスなど多くの周辺産業が関連してくる。 |

| 日本企業の駐在員派遣 |
| 東南アジア各国で、外国人の就労条件を厳しくするルール改正が相次いでいる。新型コロナウイルス禍で雇用環境が悪化し、自国民の労働者保護を重視した影響が大きい。各国に進出する日系企業にも、駐在員の派遣がスムーズにいかない影響などが出ており、現地の法令を見据えた事前準備の重みが増している。ある日系商社は当局に「日本では職種と出身学部の関連性がないことが多い」と説明したが、申請は何度もはじかれた。「担当者によっても対応がバラバラだ」という。新型コロナの影響で、当局による許可証発行の手続き自体も滞りがちという。 |
| バイ・アメリカン法 《Buy American Act》 |
| 米国は1933年バイ・アメリカン法Buy American Actを制定し、米国政府の公共事業で使用する物資・サービスについては、自国内の製品を優先的に購入することを規定した。これは、国内産業の保護および国内生産の奨励を目的とする不況対策の一つとしてとられたものであった。また、第二次世界大戦後、米国は大規模な経済援助と軍事支出を行ってきたが、ヨーロッパ諸国の生産性回復とともに米国の国際収支は赤字に向かい、海外におけるドル残高と米国からの金流出が増加し、1960年前後からドル危機が発生した。そこで、外国が米国の対外援助やドル借款によって物資を調達する場合、米国製品を優先的に購入させるバイ・アメリカン政策をとった。これは自国船を優先的に使用させるシップ・アメリカン政策とともに、ドルの海外流出を防止するドル防衛策の一つであり、また一方では国内産業の保護を目的とするものであった。2008年9月証券会社リーマン・ブラザーズの破綻を機に、世界は「100年に一度」ともいわれる深刻な金融危機にみまわれ、世界同時不況に突入した。世界各国は自国の産業を守ろうとして保護主義的措置をとり始めたが、米国でも2009年2月成立の景気対策法において、公共事業や政府調達に米国製品の優先的使用を義務づけるバイ・アメリカン条項が盛り込まれた。 世界貿易機関(WTO)の協定に違反しないよう「国際的な合意に沿って適用する」との文言が加えられたが、保護主義化を促すおそれがあるとして国内外で懸念が高まっている。 |
| 中国政府調達、国産を優先(バイチャイナ) |
| 中国が政府調達で外国製品の排除を進めていることが明らかになった。地方政府への内部通知で医療や海洋、地質調査などに使う機器315品目の購入で国産品を購入するよう指示を出した。財政省と工業情報化省が「政府調達輸入製品審査指導標準」(2021年版)という内部文書を5月に各地方政府に通知した。41分野の315品目が対象で、国産製品の調達比率を100%、75%、50%、25%の4段階で指導する内容だ。分野別では医療が200品目近くで最も多い。国民の生命にかかわるため国産化が必要と判断したとみられる。具体的には、磁気共鳴画像装置(MRI)やX線機器、外科用内視鏡などが含まれる。 米国ではバイデン大統領が7月下旬、政府調達で自国製品を優遇する「バイ・アメリカン」の強化を表明した。中国も同様の「バイ・チャイナ」を打ち出したことで、グローバル企業は事業への影響が避けられない。これまでは効率を重視してサプライチェーンをグローバルで最適化してきたが、現地への生産移管など再構築を迫られる。生産の現地化はかつて二国間の貿易不均衡が引き金となったが、現在は米中の覇権争いが根底にある。自由貿易のメリットを享受してきた企業にとって、広がる自国優先主義をいかに乗り越えるかが課題となる。 |