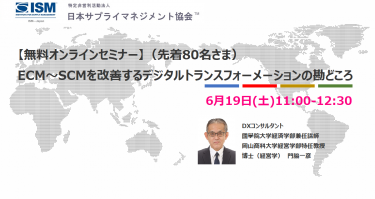3.おわりに
大きな偉業を成し遂げた日本人ゴルファーを待ち受けていたのは優勝インタビューであった。ここで米国と日本の違いをまざまざと見せつけられた。大相撲でさえ外国人力士が優勝した際、日本語である程度の感想を述べる。ところが、いくら予測していなかったとはいえ、10年近くもアメリカに住み、生活していた若者が「サンキュー」だけでは困る。確かに語学力の未熟さ、才覚というものはあるだろうが、如何に当該者が日本人社会でのみ暮らしていたかがわかる一幕だった。
企業社会でよく言われるのが語学よりも、中身だという。特にビジネスではぺらぺらと余計なことを話すより内容が大切だと、それは当たり前のことで商談中に雑談を好んでする輩はいない。但し、重要な商談の後は、国内外問わず、ゆったりした会食が待っているものだ。そこで商談の続きなど普通はしない。筆者も、厳しい商談の後、10名ほどの会食中、ペットの猫の話で1時間付き合わされたことがある。語学というより博識な欧米人の懐の広さをまじまじと見せつけられたものだ。
異文化受容能力というものがある。古くから言われてきたことだが、日本列島は海で囲まれているせいで海外との交流が少なかったことに加え、江戸幕府の鎖国政策で近隣諸国からの交易も稀少で殆ど孤立してきたという歴史がある。明治以降、積極的に海外諸国との交流を続け、戦時外交に応分の役割を果たしたとはいえ、欧米から遠隔地であったことから、意思疎通が困難であったことは否めない。かくして現下のコロナ禍では、オンライン会議が盛況だが、語学力に劣り、且つ自分の意思を明確に表明できない国民性では他国から置いて行かれる可能性は十分ある。
日本政府の外交でも同じことが言える。優秀な外交官がいるにもかかわらず外国首脳と対峙する大臣は皆通訳を付ける。通訳は数名が担当するため訳語も変わることがある。大臣がアルファベットを読めないのであれば、カタカナをふった紙でも良いので、取り巻きは何故手元に準備しないのか。大切な文言だけでも英語または当該国の言語で大きな声ではっきり発言すれば、相手の大臣の取り巻きも理解してくれる。役人達がプロトコルを偉そうに振りかざすなら実務面で表して欲しい。
二つ目
インド西部マハラシュトラ州の病院で21日、新型コロナウイルス感染症患者が使用していた人工呼吸器への酸素供給が停止し、患者22人が死亡した。同国では新型ウイルスの流行第2波が猛威を振るい、深刻な医療用品不足が生じている。事故が起きた病院前に駐車していた車両の酸素タンクから酸素が30分間にわたり漏れ、その間、重症患者60人余りの人工呼吸器への酸素供給が停止した。これを聞いて思い出すのは筆者がアフリカ・コンゴ民主共和国駐在当時、鉱山病院向けの酸素を資材調達していたが、海抜2000メートル近くの高度では乾季の時期には結構寒くなる。社宅内の暖炉で炭を燃やして眠ってしまった新婚夫婦が二酸化炭素中毒になり急遽酸素が必要となった。鉱山では、通常、工業用に酸素を120キロ離れた町のサプライヤーから調達していたが、納期は常に恐ろしくぶれていた。一般に高圧ガスと呼ばれる産業ガス・医療ガスは、水や電気と同様、経済的・社会的に不可欠な社会インフラ基盤だ。産業ガスは、あらゆる工業分野で利用され、日本のサプライチェーンを支える重要な製品だが、特に医療ガスは、患者を救うための生命線そのもの。たとえ災害時であっても、人の命をつなぎ留める医療用酸素を供給し続けなければならないといった重要な使命を担っているのが資材部門だ。途上国では酸素を確保することが優先で産業・医療などと言っていられないわけで、兎に角、安定供給の確保が第一義だった。同国では、酸素製造サプライヤーは複数でなく一社のため、彼等との普段の意思疎通や関係性が命となる。SRMの戦術がなかった時代だが売手からすれば、買手を選ぶことが出来たであろう。日本人特有の粘りと交渉力で酸素ボンベを数十本手に入れることができた。前者は根性だが、後者はより科学的だ。途上国における日本人と欧米人の関係性は、先進国に於けるそれとは異なるようだ。酸素供給者が長年に亘り同国に在住している欧州人であることから現地人のサプライヤーとは異なる交渉術が求められた。今風に言うところのSupplier Relationship Management(SRM)である。
月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA
特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会